数あるサイトの中から当ブログにお越し頂きありがとうございます。
管理人の“あんこ”と申します。
普段は3人の子供の育児や家事に追われていますが、お得情報やお金について考えるのが大好きなワーママです。
住宅購入についても記事を書いてますので、ご興味とお時間があれば立ち寄ってみて下さい。


では本題の『お金の教育』ですが、皆さんはどうされていますか?
子供を育てるようになると、子供にはお金の失敗はしてほしくないと思う方がほとんどだと思います。
そこで今回は小学生程度のお子様向けに、私がしてもらったお金の教育方法をお伝えしたいと思います。
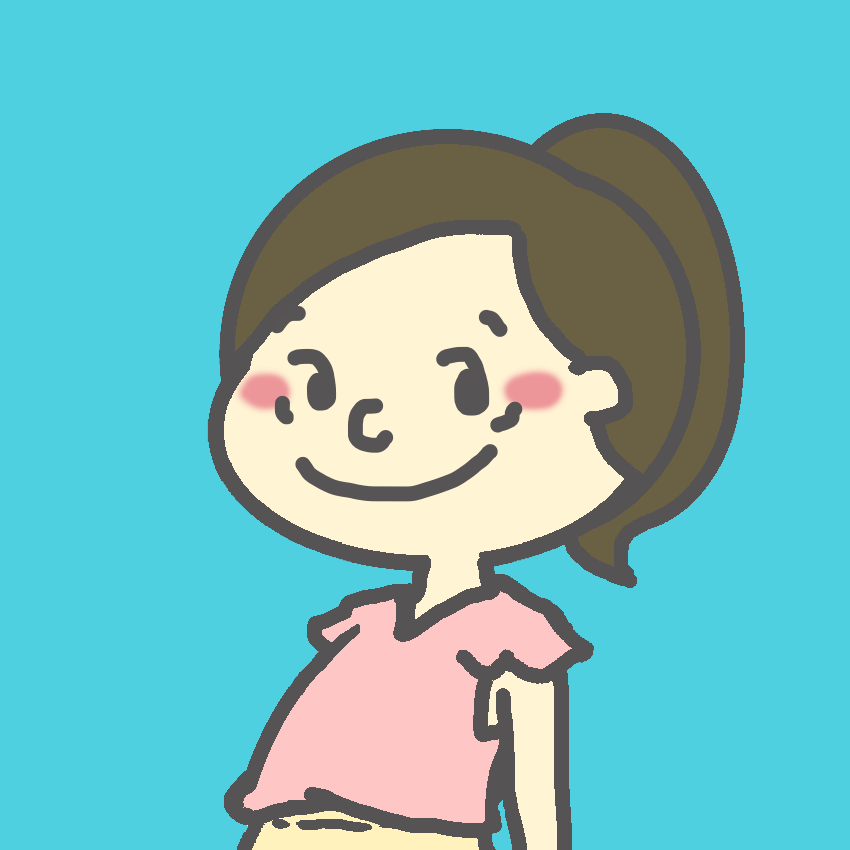
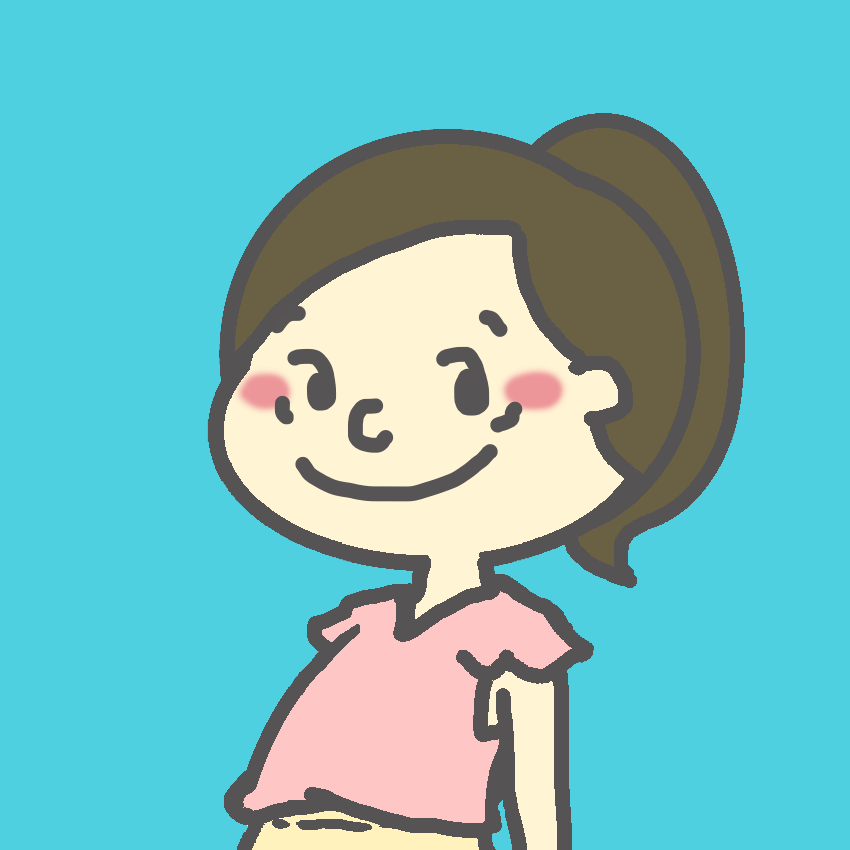
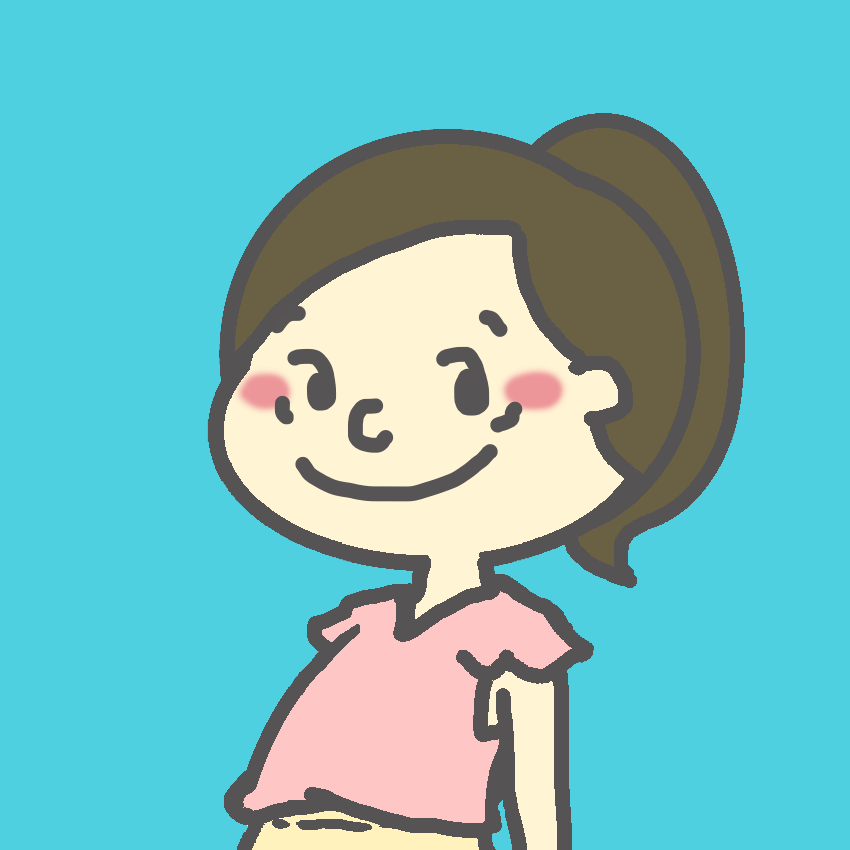
ちなみに、この方法で育ててもらった私自身はお金に困ることなく大人になりました!
なぜお金の教育が必要なの?
お金ってなに?
子供に「お金ってなに?」と聞かれて答えられますか?
- 物を買うために必要なもの
- 働いた対価としてもらうもの
- いざというときに使うために貯める物
などと、人によって価値観の変わるものです。
そしてどれも間違った表現ではないですよね。
ただ、お金でできることは大きく6種類に分かれます。
- 稼ぐ
- 貯める
- 納める
- 使う
- 備える
- 増やす
お金で出来る事ってとても多いですよね。
基本となるのは①~④になると思いますが、今後の日本で生きていくには⑤や⑥の知識もきちんと培っていかないとなりません。
経済によっても価値は変わるし、増やそうと思えば増やすこともできる。
つまり、お金の価値は人や経済によって大きく変化をしていくものになるのです。
お金に関して学ぶなら、こちらの書籍をおすすめしています。
私も実際に参考にさせてもらっているのですが、とても分かりやすく解説されています。
金銭感覚って?
金銭感覚について辞書で調べてみると、こんな風に書かれていました。
金銭の価値や使い方に対する感覚を意味する語。浪費家を指して「金銭感覚がない」と表現することがある。また、急にそれまでと桁違いの金銭を使うようになったり、クレジットカードの使用などでお金を払っているという自覚が薄れることで、「金銭感覚が狂う(麻痺する)」といわれることがある。
https://www.weblio.jp/content/金銭感覚
つまり、上記で示した「お金でできる6つの事」をバランスよく自己管理できる感覚があるかどうかが、金銭感覚のある・なしに関係してきます。
マネーリテラシーって?
そもそもリテラシーという言葉の意味としてはこちらです。
与えられた材料から必要な情報を引き出し、活用する能力
つまり、マネーリテラシー(金融リテラシー)とは、お金の勉強をして、それを活用する能力の事を言います。
この能力を高めることによって、金銭感覚が整って借金をなくしたり、ライフプランを考えてお金の使い方を整える必要があるということです。
いつから整える?
マネーリテラシーも金銭感覚も日本の教育現場ではたいして教えてくれません。
じゃあ、どこでこの感覚を学んでいくのか?
それは主に家庭です。
大体の人は、それぞれの家庭のお金の使い方から「お金とは何か」を学んでいます。
そのため金銭感覚を高めるためには、幼少期からどのようにお金とかかわってきたのかが重要になるのです。


金銭感覚の育て方
誕生日プレゼントをやめる
誕生日なのにプレゼントがもらえないなんて子供からしたら絶望的だと思います。
その代わりに1万円を渡してください。
この1万円でしてもらうことはこちらです。
- 食べたい食事を家族分用意する
- 食後のデザートも用意する
- 残ったお金は自分の好きに使っていい
食べたいものを食べるのか、欲しいものを買うために食事を節約するのか…。
予算を与えることで、お金の計算をして全員が満足する結果を出すために、子供なりにたくさん考えると思います。
ただ、子供が考える事なので夜ご飯がファストフードになることもあるかもしれません。
そこは、大目に見てあげてください…(笑)
この方法で身につくのは、予算の中でやりくりする能力です。
旅行の会計係をさせよ
小学校4年生ぐらいになるとお金をしっかり数えることができるようになりますよね?
もし家族で旅行に行く機会があれば、ぜひ会計係をやらせてみてください。
もちろん、日帰り旅行やちょっとしたお出かけでもできることだと思います。
この方法で、子供にやってもらう事はこちらです。
- 子供に旅行の予算を渡して管理させる。
- 持たせるだけでなく、支払いもすべて子供がする。
- 1日の終わりに収支報告をさせる。
非日常の中で、お金の管理をさせることで、お金に対する責任感を持たせることができ、お金にルーズになってはいけないということを伝えることができます。
あえて予定にないお店に寄って、
「これ買ってもいい?」「これ食べたいな~」
などと声をかけて、予算内に収まるものなのかを考えさせてみて下さい。
この方法で身につくのは、お金への責任感と世の中の物の価値・価格を知ることが出来ます。
お小遣いは年俸制
毎月のお小遣いっていつから始めますか?
毎月ちょっとずつ貰う家庭がほとんどかと思いますが、お年玉をある程度の額もらえる家庭であれば年俸制をおすすめします。
私の場合親戚がとても多く、お年玉だけで10万円近く頂いていました。
10万円のお年玉を12か月で割ると、月8000円程度使うことが出来ます。
環境にもよると思いますが、中学生で8000円って多くないですか?
なので、その10万円を自分でコントロールして使い道を考える事を習慣化させてしまえばいいのです。
この方法で身につくのは、予算建てすることを癖にすることです。
癖にしてしまえば、大人になってから使いすぎてしまうことを防げるのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
お金について子供に伝えるのって難しいですよね。
子供のお金教育に悩んでいる方に少しでも提案できれば…と思いこの記事を書かせていただきました。
お金の使い方は各家庭で考え方も異なると思いますので、これが正解!というものはありません。
あくまでも私が受けたお金の教育であり、皆さんがこうするべきだというものでもありません。
子供のうちにお金の失敗をしても、大人と比べて少額の失敗になることがほとんどだと思います。
そして何よりも、親がフォローしやすいですよね。
大人になってからお金の失敗をしてつらい思いをするよりも、早くからお金について子供に考えてもらう。
これはとても大切なことだと思います。
ぜひ、ご家庭でお金について考えていただければいいなと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。

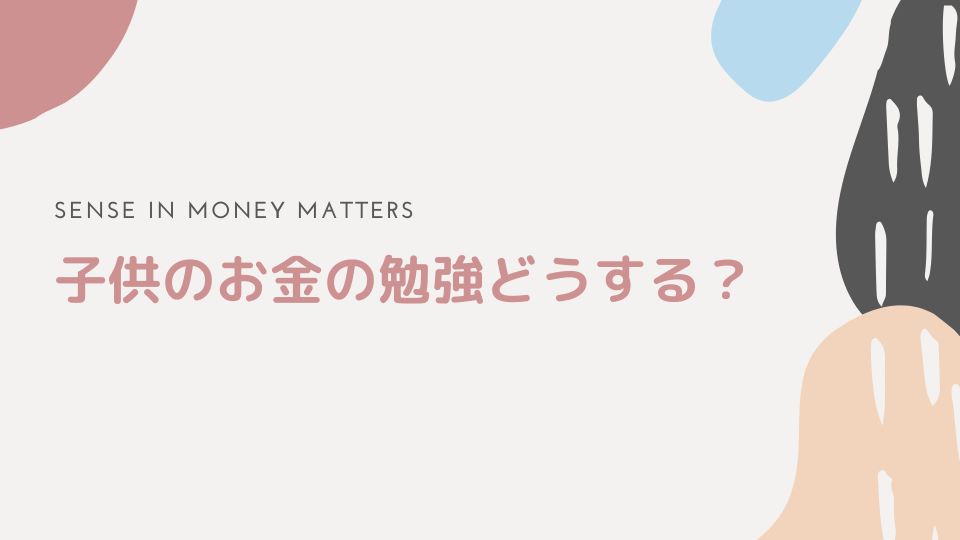
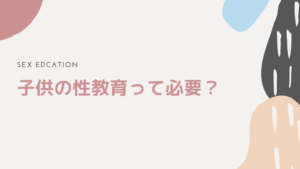
コメント